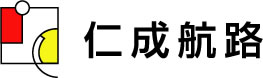東洋医学について

空腹にお酒を飲むと”五臓六腑に染み渡る“とよく言われますが、五臓六腑とは何かご存知でしょうか?
これは東洋医学で言われる解剖学分類で、五臓は精気が蓄えられ充満していることで働く臓器で、肺・心・肝・脾・腎の五つ。また六腑は普段は中空で食べ物や代謝産物が送られてきた時だけ働く臓器で胆・胃・小腸・大腸・膀胱・三焦の六つを言います。三焦は聞きなれない言葉ですが、定義がはっきりせず飲食物を吸収して全身に運ぶ血管やリンパ管のようなもの?と言われています。
近年、西洋医学で補完できない代替医療として東洋医学が見直されています。代表的な治療法として漢方薬や鍼治療、灸治療がありますが、その他にも手技療法(按摩・指圧・マッサージ・気功・吸玉・中医整骨)があります。皆さんも当院での漢方薬以外に治療を受けられたことがあると思います。かねてより東洋医学は、経験に則った治療で西洋医学のように科学的に解明されていないため、なかなか保健医療として取り入れられることが少なかったのですが、近年になりその作用機序が科学的に解明されてきました。例えば、“足の三里”というツボに鍼や灸をすると迷走神経を刺激してドーパミンが分泌され免疫機能を改善するメカニズムが分かっています。“足の三里”は特に不眠や倦怠感に有効とされており、アフリカの片田舎の診療所ではエイズにかかった多くの患者が受診しているところがテレビに映っていました。鍼や灸は医療設備のない不便な所でも安価で簡単な治療が可能になります。また、痛みにも有効であることが究明されてきています。アメリカは本格的な研究が進み、耳のツボに小さな鍼を張ると痛みが緩和されることから、陸軍では負傷して歩けなくなった兵隊に耳ツボに鍼をして自ら歩いて退却する可能性が高くなったと報告しています。また、透析医療でも血管痛に耳ツボシールを張って痛みを緩和できたという報告が見られます。
透析中にお灸は出来ませんが、痛みの少ない鍼や有効な漢方薬は可能でもっと知見を活用して皆さんに提供できればと思っています。
仁成会医師 依藤 良一